2024年シーズンのJ1リーグで熾烈な優勝争いを繰り広げた町田ゼルビア・黒田剛監督。
黒田剛監督は2023年、当時J2だった町田ゼルビアの監督に就任。
僅か1年でチームをJ1に押し上げた名将です。
青森山田高校の監督時代は冬の選手権を3度制覇、インターハイ優勝、幾多のJリーガーや日本代表選手を輩出しました。
黒田剛監督は「高校サッカー界の名将」という立場を捨て、「Jリーグの監督に就任」という新たな道を選択。
Jリーグで旋風を巻き起こしています。
今後も活躍が期待される黒田剛監督ですが、筆者は一つ気になることがあります。
それは、黒田剛監督は「なぜ周囲から嫌われているのか」ということです。
この記事では、黒田剛監督が「なぜ嫌われるのか」について、これまでの功績や過去の出来事・発言などを中心にまとめました。
町田ゼルビア・黒田剛監督は「新参者」だから嫌われる?
2024年にJ1で優勝争いを繰り広げた町田ゼルビア・黒田剛監督。
その黒田剛監督は、青森山田高校で29年間指揮を執り、全国高校サッカー選手権で優勝3度という輝かしい実績を誇ります。
高校サッカーでの実績が評価され、Jリーグ・町田ゼルビアの監督に就任。
筆者は、高校サッカー界で無双状態だった黒田剛監督の「Jリーグ監督への挑戦」を応援している立場です。
しかし、こういった「前例のない挑戦」を快く思っていないチームやサッカーファンも一定数いるのではないかと感じます。

(左)黒田剛監督 サッカーダイジェストより引用
実際、「選手としてプロでプレーした経験がない人がなぜJリーグで指揮を執ることが出来るのか」という懐疑的な考えの人が存在するのかもしれません。
確かに、そう思う人の気持ちは分からなくもないです。
「プロ」という世界は「聖域」なのではないかと感じます。
つまり、「高い実力が評価され、選ばれた者しか踏み入れることが出来ない世界」だという認識です。
「アマチュア」は広い意味で「サッカーをやりたい人なら基本的には誰でも出来る」という幅広い世界なのではないでしょうか。
無論、根本的にアマチュアの世界が無かったら、プロの世界を構築することは出来ませんが…。
そのギャップの中で、様々な議論があるのだと思われます。
プロの監督の人選に関し、「元プロ選手から選ぶのが通例だ」という感覚が日本のどのスポーツにも定着した考え方なのかもしれません。
そういった考えから、これまでずっとアマチュアの世界に身を置いてきた黒田剛監督の「Jリーグ挑戦」を心から喜べない人もいるのではないかと思われます。
確かに、その気持ちは分かります…。
それが「妬み」や「嫉妬」に近い感情として発展している可能性があるのではないでしょうか。
ちなみに筆者は、黒田剛監督の「Jリーグ監督への挑戦」を尊重したいと考える立場です。
日本のプロスポーツ界全体の監督人事に「一石を投じる出来事」だと考えています。
アマチュア選手がドラフトなどでプロ選手になり、プロスポーツの世界が構築されています。
指導者も同じく、アマチュア時代に実績を残した監督の「昇格・進出」という視点で、プロの世界へ招聘する流れは今後もあり続けて良いのではないでしょうか。
名将・黒田剛監督が嫌われる発端は天皇杯後の発言か?
町田ゼルビアは2024年6月、天皇杯2回戦で筑波大学と対戦し、PK戦の末、敗れました。
試合後、黒田剛監督は相手の「ラフプレー」や「審判のジャッジ」に怒りを露わにしました。
フラストレーションの溜まる判定があまりにも続いた。 骨折がいます。次、試合できるような怪我じゃないです。4人大きな怪我が出た以上、本当に現実を突きつけられた。何も得られないゲームだった。VARもありませんし、基準を考えるとすごく憤りを感じるゲームだった。 デイリースポーツより引用
この試合では、両チーム合わせて3枚のイエローカードが出ました。
それ以外にも激しいファウルが相次いだようで、黒田剛監督が怒りを露わにする会見に繋がったわけですね…。
黒田剛監督は、普段から「歯切れよく話をされる方」だという印象があります。
それは、喋り手としても「頭の回転が速い方」だとリスペクトしています。
黒田剛監督は、選手にどういった言葉を掛けるのかという「言葉選び」を非常に大切にされている監督です。
その黒田剛監督がため込んだフラストレーションをこれだけ吐き出すのは、あまり記憶がないかもしれません。
J1昇格1年目から町田が優勝争いに喰い込んだのは黒田剛監督の手腕が大きいと感じているのです。
そういったリスペクトを示した上で、黒田剛監督がもう少し冷静に話をされていれば「この件が大きく報道されることはなかったのではないか」と感じます。
筑波大学が相手とは言え、「J1で首位争いをしている町田が負けることは許されない」という強い気概を持って臨んでいるのは百も承知です。
その中で、試合後の記者会見というのは「ゲーム内容」や「交代カードの切り方」などを冷静に振り返るべきだったのではないでしょうか。
少し話題が逸れてしまったのが残念ではあります。
敗れた怒りや相手・審判へのフラストレーションを捲くし立ててしまった感が否めないのではないかと感じました。
こういったコメントになってしまうと、反論する方も出てきてしまうので、それが少し辛いところですよね!
これらが「嫌われる理由」に繋がってしまったり、応援してくれる人が減ったりと、黒田剛監督から人が離れていってしまいかねない要素になってしまうはずです。
筆者も「言葉選び」には一段と気を付けようと思いました。
確かに、敗れた直後ということで気持ちの作り方が難しかったと思います。
学生相手に厳しい結果になってしまったことが直接的にコメントに出てしまったのではないでしょうか。
どんな試合でも、批判やトーンダウンした言葉からは何も生まれないのではないかと感じました!
町田ゼルビア・黒田剛監督が嫌われる理由は戦術にある?
J1で旋風を巻き起こした2024年の町田ゼルビア。
その町田ゼルビア・黒田剛監督がなぜ嫌われるのかについて「戦術」という視点で見ていこうと思います。
ロングスロー多投
2024年のJ1で町田ゼルビアが優勝争いを繰り広げ、その手腕が注目を集めている黒田剛監督。
青森山田高校の監督時代からロングスローでチャンスを演出し、得点に繋げるパターンが黒田剛監督の戦術です。
町田ゼルビアの監督に就任してからも、ロングスローからチャンスを作り出す攻めは健在です。
その影響を受けてか、J1の他のチームもロングスローをゴール前に投げ込むシーンが増えています。
そもそも「ロングスロー多投」という戦術はルール違反ではありません。
これまでJリーグの各チームが使ってこなかった戦術を多投する町田ゼルビア。
筆者は、その町田ゼルビアがJ1で勝ち進んでいったことから、それに対する周囲の「やっかみ」に繋がっている可能性と感じています。
町田ゼルビアは、J1の試合でロングスローで得点に繋がることが多く、最終盤まで優勝争いを演じました。
調べてみると、町田ゼルビアのロングスローを多投するスタイルに対し、否定的な意見は思いのほか少ないようです。
町田ゼルビアを批判してる人たち、何なの?何が悪いのか、さっぱりわからないから教えて欲しい。ロングスローもボール拭くのも、違反じゃないでしょ。
— newsman_第2の人生2年目 (@newsman_1974) October 15, 2024
ロングスローを多投する戦術を取っていることが黒田剛監督の「嫌われる要因」ではなさそうです。
町田の戦い方を起点に、Jリーグでロングスローを戦術として採用するチームが増えている現状があります。
そういった意味で、「攻撃面で一つの風邪を吹かせた」と言っても良いのではないかと考えます。
ロングスローをすることで守備陣が全員自陣に戻るため、カウンターを受けにくいことが挙げられます。
また、キックと違って軌道が異なるのでクリアしにくいこともあると思われます。
オフサイドにならないなどのメリットもあるようです。
ロングスローはルール上、違反ではないことから「批判されるには少しお門違いなのではないか」と思う人も少なくないのかもしれません。
ラフプレーが原因なのか?
町田ゼルビアはJ1に上がってから、特に当たりの激しいディフェンスが目立つようになりました。
黒田剛監督はチームに「球際の強さ」や「相手のフィジカルに負けない」を求めているようです。
必死にボールを取りに行く姿勢がラフプレーに繋がっている感は否めないのかもしれません。
鬼畜の所業・町田ゼルビア pic.twitter.com/PA87jElXOW
— Lil’わかめごはん (@kyohei_breath) October 19, 2024
その割に、自分たちがファウルを受けた際にこれまでのことを棚に上げて物を言うスタイルが納得できないという方もいるようです。
これが嫌われる一つの理由に繋がっているのかもしれません…。
そういった中で懸念されるのは、頑張っている選手たちへの容赦ない言葉です。

得点後の町田の選手たち FOOTBALL ZONEより引用
筆者は、目の前の試合に勝ち、サポーターの期待に応えようと努力している選手に対して、厳しい声を掛けるのは止めてほしいと思っています。
選手も人間ですし、言われて傷付くこともあるわけです。
理想論にはなってしますが、選手の悪質なラフプレーの減少や選手や監督などを叩く言葉も無くなってほしいと思います。
モラルの面で皆がサッカーを心から楽しんで見られる日が来ることを心から願っています。
そう思っているサッカーファンは多いのではないでしょうか。
Jリーグは昇降格制度があるため、目の前の試合で何としても「勝ち点3」を上積みしなければならない都合は理解できます。
どのチームも同じ気持ちで戦っているものと思います。
そういった中で、「勝ちにこだわるサッカー」がどこまでの範囲で許容されるのかを今一度考える時期に来ているのかもしれません。
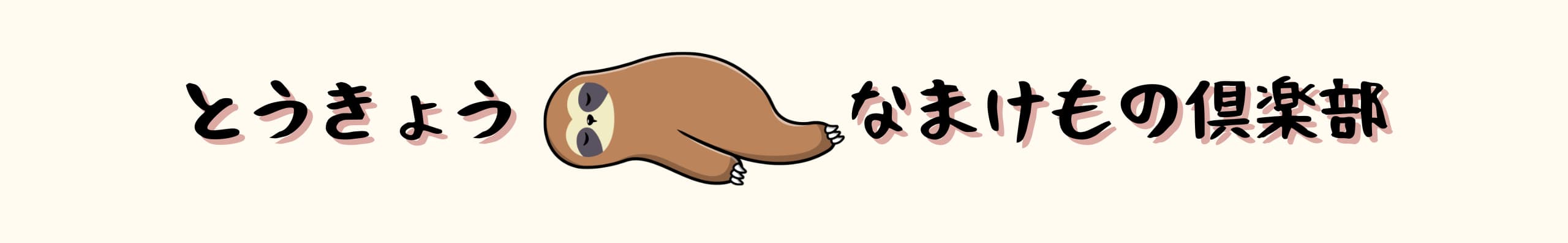






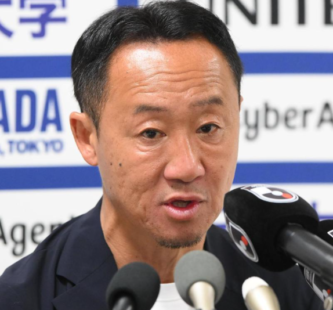





コメント