節分は例年だと2月3日にあたりますが、2025年の節分は「2月2日」です。
なぜ2025年は「2月2日」に節分なのでしょうか…?
筆者は、子供の頃、よく節分の日に自宅の至る所で豆まきを行い、それを回収して、家族全員で食べるのが恒例でした。
2025年の節分は、1日前倒しになることを最近知りました…!笑
恥ずかしながら、今年に入ってからです。
ちなみに、2月2日が節分の日となるのは2021年以来、4年ぶりのようです。
この記事では、「2025年の節分はなぜ2月2日なのか?」などについて、まとめました。
2025年の節分はなぜ2月2日なのか…?
「鬼は外、福は内」の掛け声を聞くと、「今年も節分の季節がやってきた…!」としみじみ感じます。
「節分」の由来は旧暦の立春が新年であったため、その前に邪気を払う目的で始まったとされているようです。
また、節分には「季節を分ける」という意味があるようです。
基本的には毎年2月3日の日に行われる行事です。
全国の一般家庭では、自宅で豆まきを「邪気を払い、家族が一年間健康で過ごせるように…」という願いを込めて行うものです。
筆者も保育園や小学生の頃、毎年のように自宅で行っていました。
当時は、節分の日に「豆をまく」という本当の意味を理解できておらず、豆を投げるという行為が「単純に楽しいから」という理由で行っていました。
大人になって、一人暮らしを始めてから15年ほどが経ちました。
その影響で節分行事を行うことはめっきり減りました。
あの時、もう少しその意味を理解した上で節分を迎えていたら、どうなっていたかなとも感じます…。
春の訪れや暦上の季節の分かれ目の日であることに対し、もっと思いを馳せることができたかなと感じています。
大人も子供も一緒に行えるのが「節分」ですが、2025年の節分は「2月2日」です。
良運を運んでくると言われる方角は「西南西やや西」となっています。
皆が節分の日に西南西やや西の方角を向きながら、恵方巻きを食べるのですね!
筆者も実際に2月2日の節分の日に西南西やや西の方角を見て、恵方巻きを頬張りました。
「今年も健康で過ごせると良いな…」という思いでした。
ここ十数年は恵方巻きを食べることが無かったので、今年は良いこともあったら良いです!笑
そもそも、例年だと2月3日が「節分」であるのが基本的には多いのですが、なぜ2025年は2月2日なのでしょうか…?
節分の日は、立春の日の前日に設けられています。
節分の由来に関してですが、「立春」は暦の上で「春が始まる日」とされています。
その前日である「節分」は「冬の最後の日」という由来が語源になっているようです。
節分の由来には「季節を分ける」という区切りとしての意味があるのですね!
節分は毎年2月4日に迎えることが多いため、その前日にあたる2月3日が「節分」として恒例行事になっているようです。
それが2025年は2月3日に「立春」となる関係で、その前日の2月2日が「節分」の日となります。
このように、必ずしも毎年2月3日が「節分」になるとは限らないようです…。
今年の節分の日が2月2日になる謎についてわかったこと
・節分とは→立春の24時間前の日
・立春とは→立春点(太陽黄経315度になる瞬間)が含まれる日
・いつ立春なのか→国立天文台が年に1回発表
・現在の暦は1年が基本365日だが、1太陽年(地球が太陽の周りを1周する時間)は365日と5時間48分46秒— ののはらすずめ (@nonoharasuzume) January 16, 2025
前回「2月2日」に節分を迎えたのは2021年ですが、その前は明治30年の1897年だそうです。
気が遠くなるくらい前の話ですよね…!
それだけ2月2日に「節分の日」を迎えることは歴史的にも極めて珍しいことと言えるのではないでしょうか。
ちなみに2026年、2027年は例年通り「2月3日」に「節分の日」を迎えることになっています。
筆者は、現在30代前半なので、2月2日に節分を迎えるのは人生で2度目となります。
そう考えると、2025年の節分に対して「例年とは違う今年の節分」という意味でも思いを馳せることができるのかもしれません…!
自宅で豆まきはしないかもしれませんが、節分当日に2025年の恵方である「西南西」の方角を向きながら、恵方巻きを頬張ることは出来ますよね!
実は久々にしました!笑
人それぞれ、時の流れの感じ方はそれぞれですが、大人になると、あっという間に時間が経過るのではないでしょうか。
それによって何だかしんみりしたり、急に胸が締め付けられるような切なさを感じたりすることが以前より増えた気がします。
それは、自我の芽生えや目の前の仕事や趣味に全力投球している証とも受け取れます。
内心は「子どもの頃のようにもう少し時間の経過をゆっくり長く感じていたい…」という思いがあるのも事実かもしれません…。
季節は、皆に平等な速度で訪れるはずなのに、大人になればなるほどそのスパンを短く感じてしまいます。
年齢を重ねることに対して、遠慮をしてしまう自分がいるのもまた事実です。
「また今年も健康な状態で節分を迎えられた…」と安堵や感謝の気持ちだけで当日を迎えられたら何も問題ないはずなのですよね!
でも不思議な事に大人になると、その節目を額面通り喜べない自分もいるのです…!笑
意外と知らない…?地域によって節分の日の過ごし方が違う!
2025年の節分は4年ぶりに2月2日です。
一般的には、自宅で鬼に対して豆をまくのが、各家庭でお馴染みのことかと思います。
その豆で大豆を使うという地域もあれば、落花生を使用する地域もあるようです。
筆者は、雪深い東北地方の出身なのですが、子供の頃から「節分の豆まき=落花生」でした!
父親に聞いたところ、「あまり詳しくは分からないけど、恐らくは回収する時の手間を省くために大きめの落花生を使うのだと思う…」という返答が返ってきました!
筆者の父親は、超が付くほどめんどくさがりな性格なのです。
回収する時のことを考えると合理的であるため、思わず「なるほど!…」と思いました。
筆者の実家は沿岸沿いにあり、冬場は自宅が偏西風を目一杯浴びることになります。
その寒風が雪囲いの合間を縫いながら、自宅にぶつかってきます。
そのため、自宅の座敷や西側の部屋は自宅内でも室温が冷え込み、氷点下まで下がることもあります。
「豆の回収の苦労をできる限り最小限にしたい…」という考えの末、理に適った形で落花生使用に至ったようです。
ちなみに父親は、落花生をまく専門であり、回収作業は大変なので自ら買って出ることはほぼ無いです…!笑
東北地方は雪国であり、無事に節分の日を迎えたとしても、寒さが和らいだり、積雪量が減ったりすることはありません。
暦上では節分の由来でもある「冬の最後の日」から「春の始まり」である立春に切り替わる日です。
筆者が幼い頃は、節分の意味をそこまで理解していませんでした。
しかしながら、こうやって考えると、雪国の方々にとって節分は由来通り「冬の最後の日」、即ちめでたい日なのかもしれませんね!
関西を中心に、節分の日に良運を呼び込むとされる方角を向きながら、恵方巻きを食べる風習も一般化しているようです。
筆者の実家がある地域では、恵方巻きを扱うスーパーはあるものの、各家庭にそこまで定着していないような印象を受けます。
それでは「節分の夜に何を食べるのか?」と言いますと、筆者の地元では冬場にハタハタがよく釣れます。
冬場の今の時期は、ちょうど産卵のため多くのハタハタが漁港に訪れるため、多くの釣り人で賑わいます!
筆者の実家では節分の日にハタハタを焼いて、田楽にして食べることが恒例化しています。
また、ハタハタは幸福を呼び込む魚とされているため、1年のスタートを切る上で縁起の良い魚となっています。
そのハタハタの田楽とともに、納豆ご飯と地元の郷土料理である納豆汁が食卓を彩ります。
納豆を食べることで「その年の無病息災を願う」や「万病の根が抜けていく」という言い伝えがあるとされています。
筆者も子供の頃から、「納豆」はソウルフードとして親しみを持っていました…!
その納豆とともに、山菜やきのこ、すり鉢で潰した納豆、豆腐、ネギなどが入った具沢山の納豆汁を食べると体が芯から温まります。
「今年も一年頑張って過ごそう…!」と思えるようになります。
全国各地では、節分当日に「何を食べるか」について、様々な食文化が点在しています。
調べた結果、青森では鯨料理、西日本では鰯の焼き魚、島根県ではナマコの酢の物などがあるようです。
各地でそれぞれの伝統にあやかり、様々な「食」を通じて節分を充実した形で過ごそうとしていることが分かりました!
それだけ分かっただけでも、心がほっこりしました。
また、筆者の実家は米農家であるため、節分の日は必ず新米が食卓に並びます。
その上に納豆をかけて食べるのが定番なのです。
炊き立ての新米は艶、食味ともに申し分なく、粒の甘みを感じながら食べる納豆ご飯は至極の味です。
思わず「これ以上に美味しい食べ物は果たして世の中に存在するのだろうか…」という気持ちになるのが筆者の節分のルーティンでもあります!笑
2025年は2月2日に節分の日です。
筆者は一人暮らしのため、豆をまくことはありませんでした。
西南西やや西の方角を見ながら恵方巻きを食べ、暦上の旧正月である「節分」に願いを込めながら楽しみました!
2025年に「大病することなく、健やかに過ごせますように…」という願いはあったので、良い形で節分の日を迎えられました。
来たる2月2日の節分に向けての周囲の反応…!
2021年以来となる2月2日の節分。
世間では2月2日に節分を迎えることに対し、どのようなリアクションがあるのでしょうか…?
2月3日が毎年の節分なので、現時点でまだ気付いていない人もいるかもしれません…。
例年と異なり今年の立春は2月3日です
つまり、節分はその前日の2月2日恵方巻きの準備とか間違えないようにしないとですね#節分#恵方巻き
— もけけ (@mokekemokeke125) January 16, 2025
今年の節分は2月2日👹
124年ぶりに2月3日が節分じゃなかった
2021年以来4年ぶり😶😶2月3日は立春🌸🌸
2月3日が節分だと思ってました💦
どうしましょー。3日に恵方巻き
作ろうとしてました…😮— 三吉梨香 (@rika_mi_yo) January 16, 2025
そうなんです!!!2月2日!!!
うち息子が2月3日産まれで、保育園の時に
「なんで俺の誕生日やのに鬼に追いかけられなあかんねん…」ってめっちゃ拗ねてうちでは節分封印になりました……!!
今年は思いっきり節分する!!!
(ノ・ω・)ノ⌒◦⚬¨°。゚— ななな( 鎌屋のお嫁 ) (@ymgchiyoichi723) January 16, 2025
3つほど抜粋してお伝えしましたが、ほとんどの人は2月2日だと気付いている方が多いようです。
恵方巻きや大豆、落花生の準備をしたり、縁起物などの島を作ったりと、直接的に影響があったのは販売側だったのではないでしょうか。
2024年に良いことが巡ってこなかった人は、恵方の西南西やや西の方角を向きながら、恵方巻きを食べて良運をたぐり寄せたい一心ですよね…!
改めて、スーパーの役割は重要ですよね!
筆者は上京して、数年が経ちます。
雪国で育った筆者からすると、東京は「四季の移り変わり」をあまり感じられず、気付いたら季節が変わっていたということが多かったです…。
その意味で「節分」は四季を感じる上でも大切な行事です。
そう考える中で、私の地元の東北では冬季間は気温だけでなく、雪や霰、吹雪、つらら、路面の凍結などがあります。
幼い頃は、生活する上でどこか厄介だなと感じていました。
年齢を重ねる上で「季節の変化が目に見えて感じられる瞬間というのは非常に尊いものだな…」としみじみ感じています。
子供の頃は、凍結した路面で何度も転びました。
車を運転する際にはアイスバーンで肝を冷やましたし、冬は最も過ごしにくい季節として位置付けていた自分がいました。
そんな自分が東京に来て感じるのは「四季を感じられることへの喜び」です。
冬の最後の日を指す由来の「節分」もその一つです。
「節分の日」を無事に迎えることは、筆者にとって、年齢をまた一つ加えたことを意味するのかもしれません。
しかし、それ以上に「今年も無事、節分の日を迎えられた!」という感謝の気持ちを持つことから始めたいです。
その上で、無事に2月2日を過ごすことができれば、それ以上の幸せはないのではないかと感じます。
これから年齢を重ねるごとに、時間が経過する速度の感じ方はさらに加速していくものと思われます。
その中で今回の2月2日の節分もそうなのですが、冬の最後の日という由来を持つ節分をどう過ごすのかは改めて大切な気がします。
そういった一つ一つの節目をタイミングとして捉えられるかどうか…。
「自分がどのような気持ちで節分を迎え、どう刻んでいくのか」が生きていく上で重要なのではないかと考えさせられました。
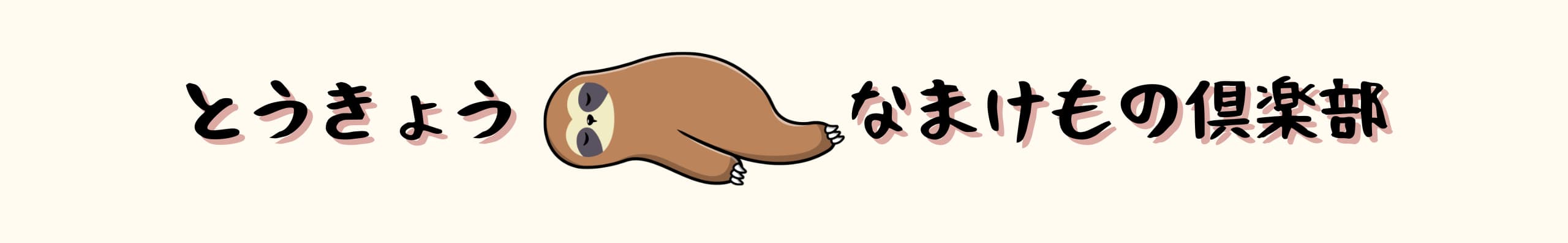














コメント